※この記事にはアフィリエイト広告が含まれております。
💡この記事はこんな方におすすめです
- 「育休を取りたいけど収入が不安…」をスッキリ解消したいパパ
- 出生後休業支援給付金(上乗せ13%)のポイントを手早く把握したい人
- 月末・14日ルールなど“損しない”日程設計のコツを知りたい家庭
- 申請の流れや社内調整の伝え方まで、具体策がほしいワーキングパパ
- 出産育児一時金・社会保険料免除まで含めた家計インパクトを全体最適化したい人
🐾 はじめに
「育休取りたいけど、お金が不安…」
「結局なにがもらえるの?」
わたしも最初は同じでした。
収入は減るのか、申請は難しいのか、職場にどう伝えるのか…。
ここでまず知っておきたいのが、
2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」。
これは、産後すぐ(原則8週間以内)に取得できる
産後パパ育休(出生時育児休業)や、その後の育児休業に上乗せされる給付で、
賃金日額×休業日数(上限28日)×13%
が支給されます。
既存の育児(・出生時)休業給付金(67%→50%)と組み合わせると、
実質手取り“ほぼ満額”に近づくのがポイント。
制度的に「パパも関わろう」を後押ししてくれる、まさに追い風です。
🐾 出産・育児、お金のまとめ(2025年版)
① 出生後休業支援給付金(新設)
・対象:産後パパ育休(出生時育児休業)または育児休業の取得者で
要件を満たす場合に上乗せで支給
・金額:休業開始時賃金日額 × 対象日数(上限28日)× 13%
・ねらい:産後直後の関わりを後押し。
既存の給付と合わせた“実質手取り100%相当”をめざす位置づけ。
計算例
月給30万円・28日取得なら、賃金日額1万円×28日×13%=3万6,400円が上乗せの目安。
② 出生時育児休業給付金・育児休業給付金(雇用保険)
67%(育休開始~180日)→50%(181日目~)で支給。
産後パパ育休も対象。支給は原則2か月ごとの支給単位期間で進みます。
給付は非課税、かつ申出により健康保険・厚生年金保険料が免除
(在職で給与なしの場合、雇用保険料負担もなし)。
そのため「給付80% ≒ 手取り10割相当」になりうる仕組みです。
③ 出産育児一時金(医療保険)
原則50万円/児。直接支払制度を使えば病院へ直接支給され、
窓口では超過分のみ支払い。多胎なら胎児数分。
④ 社会保険料の免除の考え方(重要)
月末時点で育休、またはその月に14日以上の育休があると、
原則その月の健康保険・厚生年金が免除に。
月またぎ・賞与月の扱いなど注意点もあるため、
人事と事前に日程設計を。
ここまでの要点
- 「非課税+保険料免除」で実質の手取りは給付率以上になることが多い
- 産後直後は上乗せ13%が効き、実質満額に近づく
- 月末・14日ルールを意識すれば、家計インパクトをさらに最適化できる
🐾 家族のスタートダッシュに、パパの“本気”を
産後8週間は、家族の「土台づくり」の時間。
ここでパパが“いて当たり前”になると、
その後の家事育児の分担・コミュニケーションの質が一気に変わります。
わたしは退院直後から1週間休み、
ミルク作り・おむつ替え・沐浴・寝かしつけを徹底的に練習。
コツは3つ。
①役割の見える化:
ミルク担当・沐浴の段取り・夜泣き対応を「誰が」「いつ」「どうやるか」決めておく
②“段取り勝ち”の習慣:
哺乳瓶の洗浄・消毒を先回り、沐浴の準備をチェックリスト化
③抱っこの“引き出し”:
縦抱き・Cカーブ・歩き抱っこ…泣き止まない日は“試行錯誤こそ正解”
産後すぐの1週間で、「パパがいると回る」という実感を家族全員が持てると、
ママの回復が進み、赤ちゃんも安心、パパの自信も上がる。
この積み重ねが、のちの職場復帰期のチーム力を生みます。
🐾 パパ育休、いつがベスト?(2段階モデル+準備)
第1段階:産後すぐ(出生後8週以内)— 最大28日が勝負
・産後パパ育休(出生時育児休業)+出生後休業支援給付金 のゴールデンコンボ
・条件を満たせば、実質手取り100%相当に迫る設計(給付80%+非課税・保険料免除)
・やること:
産後ケアの主担当/夜間シフトの整備/
家事の完全代替(洗濯・食器・掃除・買い物の定型化)
第2段階:ママの職場復帰にあわせて(生後6か月〜1歳)
・育児休業給付金(67%→50%)を活用し、ワンオペ回避のバックアップ取得
・「保育園慣らし+復帰後1〜2週間」を中心に短期取得すると、家庭・職場の負荷分散に効果大
・月末 or 14日以上を意識した日程設計で家計を最適化(人事へ早めに相談)
🐾 育休前にやっておくべき準備リスト(支えになるモノ)
(1)会社まわり
・上司・人事へ早期相談(理想は妊娠判明後)
→取得時期・分割回数・引き継ぎ計画・代替体制をセットで提示
・就業規則・育休規程の確認
→分割取得回数、就業可能時間(産後パパ育休中は就業10日または80時間まで)、
申請様式・締切などを整理。
・支給タイムラインの把握
→育児休業給付は2か月ごとの支給サイクル。家計のキャッシュフローを見える化。
(2)家庭まわり
・役割分担の合意(夜間授乳・沐浴・通院・買い物・家事)
・1日の行動表(赤ちゃんのリズムに合わせたタスクの“時限式”化)
・最低限の便利アイテム(抱っこ・沐浴・消毒の時短グッズなど、家計に無理のない範囲で)
(3)お金まわり
・収入見込みの試算:67%・50%・上乗せ13%を当てはめる簡易表を作成
(手取り=課税なし&保険料免除の影響も考慮)
・出産育児一時金の確認:直接支払制度を使えるか病院に事前確認。
・社会保険料の免除:月末/14日以上の条件に注意。賞与月の扱いは要確認。
🐾 注意すべき3つのポイント(失敗回避のコツ)
①申請タイミングに要注意
育児休業給付・出生後休業支援給付金ともに、育休開始後に会社経由でハローワークへ。
書類の遅れは支給の遅れに直結。
社内の担当者と締切を共有し、取得前に書類の型をそろえるのが安全です。
②職場への伝え方で成功率が変わる
「育児のため休みます」より「家族と社会のために、計画的に育休を取りたい」と
目的・期間・引き継ぎ案までセットで伝える。
上司にとっても “判断材料” が増え、合意形成が進みます。
③復帰後の働き方は“前倒しで合意”
いきなりフルスロットルが難しければ、短時間勤務やフレックスの活用も検討。
保育園慣らしや通院など、最初の数週間の “ゆとり” を確保しましょう。
制度は会社差が大きいので、就業規則を読み込み→人事とすり合わせが必須。
🐾 申請の窓口&タイムライン早見(保存版)
・対象の主役は雇用保険
出生時育児休業給付金/育児休業給付金/出生後休業支援給付金は、雇用保険の制度。
基本は会社経由でハローワークに申請(個人申請が必要な書類も一部あり)。
・スケジュール感
産後パパ育休は出産の翌日から起算して8週間内で最大28日・2回まで分割可。
期間中の就業は最大10日(または80時間)まで。
出生後休業支援給付金は、対象給付(産後パパ育休 or 育休)を
通算14日以上取得等の要件を満たすと上乗せ支給。
金額は賃金日額×日数(上限28)×13%。
・医療保険ルート
出産育児一時金(50万円)は、加入している健康保険等から支給。
直接支払制度を使えば病院へ直接振込、窓口負担は超過分のみ。
🐾 わたしの実例から:月末テクと心構え
2回目の育休は短期(3日)でも、
月末を含めた取得で保険料の扱いが有利になる場合があります。
さらに、14日以上の取得で免除対象になる月の作り方も検討の価値あり。
いずれも会社の勤怠ルールと整合が必要なので、
人事とカレンダーを一緒に見ながら決めるのが確実です。
心構えとしては、「段取りは愛」。
ミルク・沐浴・寝かしつけの勝ちパターンを家として確立できると、
ママも赤ちゃんもパパもラクになります。正解はひとつじゃありません。
仕事と同じで失敗→修正の繰り返しで、ちゃんと家族の “型” ができます。
🐾 さいごに
育児はチーム戦。
パパが関わると、家族はもっと強くなる。
制度はどんどん整ってきました。
2025年4月は、その象徴的な節目。必要なのは、“知って、計画して、動く”だけ。
「完璧じゃなくていい。できることから一歩ずつ。」
わたしたちの毎日の小さな一歩が、子どもたちの未来を形にしていきます。
今日も一緒に、前へ進みましょう。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
少しでも読者のみなさんのためになる記事作りにこれからも努めて参りますので、
評価していただけるととても励みになります☆
「こどもたちの未来をもっと明るくしたい」だから行動する。
それでは今日も元気にいってらっしゃーい(`・ω・´)ゞ
あるいはおやすみなさーい(。-ω-)zzz. . .

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4eff98e9.ff5b37db.4eff98ea.89ab46bf/?me_id=1410329&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fairricobaby%2Fcabinet%2Fimgrc0098763826.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4effc002.9c06f8ad.4effc003.2f0f07e9/?me_id=1273051&item_id=10004500&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcaizu-corporation%2Fcabinet%2Fevent%2Fsupersale%2F2512sstop%2Fcb03-daisy-top.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4688593b.08a57964.4688593c.a46335be/?me_id=1212232&item_id=10042795&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnetbaby%2Fcabinet%2F184%2F405184.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4688593b.08a57964.4688593c.a46335be/?me_id=1212232&item_id=10043099&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnetbaby%2Fcabinet%2F892%2F4902705095892.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4fc206cd.8146839c.4fc206ce.7f590d5c/?me_id=1429259&item_id=10000005&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwhitehalca%2Fcabinet%2F325625318309918.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dda0f88.aa2f1ddd.4dda0f89.88a9c81a/?me_id=1398103&item_id=10000878&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpeapod%2Fcabinet%2F08465326%2Fomocya14-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ccf1a89.edf8d72e.4ccf1a8a.557243ae/?me_id=1211066&item_id=10027038&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoolandmeal%2Fcabinet%2Fitem%2F11429857%2F05086290_th_04.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4688594f.b2703039.46885950.4d601d1c/?me_id=1396364&item_id=10000136&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flarutan%2Fcabinet%2Flarutan%2Fn100-r%2Fn100-search-image%2Fn100-c1-top.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e4927ca.f15fc91d.4e4927cb.b03a03d5/?me_id=1303383&item_id=10000582&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbabycresco%2Fcabinet%2Falobaby%2Fmilklotion%2Fmilklotionbig%2Falobaby_09a_kaori.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4688593b.08a57964.4688593c.a46335be/?me_id=1212232&item_id=10004203&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnetbaby%2Fcabinet%2F184%2F400184.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4effac59.15c43dcc.4effac5a.b3dccaa0/?me_id=1344400&item_id=10000030&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsorasion%2Fcabinet%2F06829153%2Fimgrc0107050852.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4effb03d.40b940e2.4effb03e.dc821d9b/?me_id=1355510&item_id=10000079&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkyowashokken%2Fcabinet%2F09062900%2Fhtaro-3-pkg-50off-v2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46885933.d3fd02a2.46885934.383fde5f/?me_id=1273476&item_id=14624897&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frcmdse%2Fcabinet%2Fkr21%2Fkr-4973655413104.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39d68261.23cb3c1a.39d68262.51caa87f/?me_id=1350960&item_id=10000941&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarine-blue%2Fcabinet%2Fshohin7%2Fbabys269.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d4205d8.36f200b2.4d4205d9.51b3a357/?me_id=1363217&item_id=10000301&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamabikoya%2Fcabinet%2F08468188%2F12435093%2Fmoku_top2509.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4effbd91.5dd42e62.4effbd92.cdf96f73/?me_id=1388676&item_id=10000228&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcareland%2Fcabinet%2F09242132%2Fcompass1670227464.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
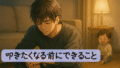

コメント