※この記事にはアフィリエイト広告が含まれております。
💡 この記事はこんな方におすすめです
- 子どもの夜泣きや寝かしつけで、自分の睡眠時間が削られているパパ
- 朝起きても疲れが取れず、仕事や家事に集中できないと感じるパパ
- 子どもが寝たあとについスマホを見て夜更かししてしまうパパ
- 仕事と育児の両立に追われて、自分の健康を後回しにしているパパ
- 家族のためにもっと元気でいたいけれど、何から整えればいいのかわからないパパ
🐾 パパの睡眠不足が深刻化している現状
「寝ても疲れが取れない」
「子どもを寝かしつけたのに、自分は眠れない」
そんな悩みを抱えているパパ、多いのではないでしょうか。
わたしもそのひとりでした。
子育て中の夜は授乳や夜泣き、寝かしつけで自分の時間が削られがち。
やっと一息つけるのは子どもが寝たあとのわずかな時間ですが、
その時間についスマホを見てしまい、翌朝ヘトヘトに…。
これ、パパあるあるですよね。
でも実感しているのは、
「パパが元気でいられることは、家族全体の笑顔につながる」ということ。
今回は、忙しいパパでも
すぐに取り入れられる「眠りの質を高める6つの工夫」をご紹介します。
1. スマホのブルーライトがパパの睡眠を妨げる理由と対策
子どもを寝かしつけてやっと訪れる「自分時間」
SNSをチェックしたり動画を見たり…
ほんのつもりが1時間経っていた、なんて経験ありますよね。
実はこれ、単なる夜更かしではなく、睡眠の質を下げる原因にもなっています。
スマホのブルーライトは脳を「まだ昼間だ」と錯覚させ、
眠りを促すホルモン(メラトニン)の分泌を妨げてしまうんです。
その結果、眠りが浅くなったり翌朝の疲労感につながったりします。
わたし自身も夜のスマホ習慣に苦しんでいましたが、
ブルーライトカット眼鏡をかけるようにしただけでもだいぶ違いました。
「完全にスマホ断ち」は難しくても、
こうした工夫で目や脳への負担を減らすだけで、寝つきが改善されますよ。
さらにおすすめは「寝室にスマホを持ち込まない」こと。
リビングで充電して、ベッドには持ち込まないルールを決めるだけで、
眠りの質は大きく変わります。
2. 子どもと一緒に整える体内時計|光と温度の調整法
「子どもがなかなか寝ない」「朝の目覚めが悪い」——
そんな悩みを解決するカギは“体内時計”にあります。
これは子どもも大人も共通で、生活リズムを整える大切な仕組みです。
朝はカーテンを開けて自然光を浴びることで、
脳が「1日のスタートだ」と認識し、夜の眠気もスムーズに訪れます。
わが家では息子と一緒にカーテンを開けて
「おはよう!」と声をかけるのを習慣にしていますが、
これだけでも生活リズムがかなり安定しました。
夜は逆に、暖色系のやわらかい照明に切り替えるのがおすすめ。
強い白い光は眠りのスイッチを妨げるため、
調光できる間接照明を取り入れると効果的です。
わが家も照明を変えてから、子どもの寝つきがスムーズになりました。
また、寝室の温度も見落としがちですが重要です。
寝入りは少し涼しく、明け方は少し暖かくなるようにすると深い眠りを保ちやすくなります。
静音タイプのサーキュレーターや加湿器を使うと快適に調整できますよ。
3. 仕事モードから育児モードへ|心の切り替えルーティン
布団に入っても
「明日の会議どうしよう」
「あのメールまだ返してない」
などと仕事が頭を離れないこと、ありませんか?
この“仕事脳”のままでは眠れないのも当然です。
そして子どもは親の気持ちを敏感に感じ取るので、
パパがピリピリしていると安心して眠れません。
そこで大切なのが「切り替えルーティン」
わたしの場合、寝る前に3行だけ日記を書くことを習慣にしています。
「今日嬉しかった子どもの一言」や「感謝していること」を書くだけで、
気持ちがふっと穏やかになるんです。
さらに、アロマディフューザーを寝室に置くようにしてから、
切り替えがよりスムーズになりました。
ほんのり香るアロマはリラックス効果があり、
子どもも自然と落ち着いて寝つきやすくなります。
香りの力は思った以上に効果的ですよ。
呼吸法(4秒吸う→7秒止める→8秒吐く)もおすすめ。
副交感神経が働き、自然に眠りに入りやすくなります。
大切なのは「毎日同じことをする」こと。それが眠りへの合図になるのです。
4. 夜泣き・中途覚醒との上手な付き合い方
子育てパパの宿命ともいえる「夜泣き」や「夜中の中途覚醒」。
せっかく眠れそうだったのに…とがっかりする瞬間、ありますよね。
でも、赤ちゃんの睡眠リズムは大人とは違い、成長の一部。
夜中に目を覚ますのは自然なことなんです。
大事なのは「どうにか泣き止ませなきゃ」とひとりで背負い込みすぎないこと。
パパにできるのは環境を整えたり、ママと分担したりすることです。
わが家では、夜泣きのときに授乳ライトのような小さな明かりを使っています。
部屋全体を照らさずに済むので、子どもも再び安心して眠りにつきやすいです。
抱っこや水分補給など、
ちょっとしたサポートでもママにとっては大きな安心感につながります。
夜泣きをゼロにすることは難しくても、
パパが「隣で一緒にいる」ことが家族の安心感につながるのです。
5. 昼間にできる睡眠負債解消テクニック
子どもが小さいうちは、夜まとまって眠れないのは仕方のないこと。
だからこそパパ自身が「昼間に少しでも回復する工夫」を持つことが大事です。
おすすめは昼休みの10〜15分仮眠。
30分以上寝ると逆にだるくなるので、短時間の「パワーナップ」がベストです。
わたしはオフィスでアイマスクを使って目を閉じるだけの仮眠を取り入れていますが、
午後の集中力がまるで違います。
また、昼間に外に出て自然光を浴びるだけでも体内時計がリセットされ、
夜の眠りにつながります。
コーヒーなどのカフェインは夕方以降は避けるのがポイント。
代わりにカフェインレスコーヒーにすると安心です。
「夜眠れないから仕方ない」と諦めるのではなく、
昼間に小さな休息を積み重ねること。それが家族時間を守る大きな力になります。
6. 睡眠環境を整えて家族時間の質を向上させる方法
最後に伝えたいのは、パパの睡眠は「体力回復」以上の意味を持つということ。
眠れている日は子どもと笑顔で遊べるし、ママにイライラをぶつけることも減ります。
その違いを生むのは、毎晩の眠りの積み重ねです。
わたし自身、寝具を変えたときにその効果を実感しました。
体に合った枕やマットレスを使うと、起きたときの体の軽さが全然違うんです。
「眠りに投資することは、家族に投資すること」だと本気で思います。
「今日は疲れているから…」と遊びを断るか、
「ちょっと遊ぼうか!」と声をかけられるか。
パパの眠り次第で未来の思い出が変わります。
🐾 よくある質問(FAQ)
※私が代表を勤める子育てサロンで出てきた意見をシェアします☆
Q1: 夜泣きがひどくて全く眠れません。いつまで続きますか?
A: 夜泣きのピークは生後3-4ヶ月頃で、多くの場合1歳半頃までに自然と落ち着きます。
個人差はありますが、適切な対策で軽減可能です。
Q2: 仕事が忙しくて昼寝の時間がありません
A: 10-15分の「マイクロスリープ」でも効果があります。
車内や休憩室で目を閉じるだけでもリフレッシュできます。
Q3: 妻との夜泣き対応の分担はどうすべき?
A: 平日は交代制、週末はパパが多めに対応するなど、
お互いの負担を考慮したルール作りが大切です。
🐾 まとめ|パパの睡眠改善で得られる3つの効果
「寝ても疲れが取れない」
「子どもに起こされて眠りが中断される」
そんな毎日の中で、パパ自身の睡眠を後回しにしてしまうのは自然なこと。
でも、だからこそ意識的に眠りを整える工夫が必要です。
今回紹介した工夫は、どれもすぐに実践できるものばかり。
- 就寝前のスマホを手放す(ブルーライトカット眼鏡)
- 光と温度で体内時計を整える(調光ライト・サーキュレーター)
- 仕事脳からパパ脳への切り替えルーティン(アロマ)
- 夜泣きへのシェア姿勢(授乳ライト)
- 昼間の小さな休息(アイマスク・カフェインレス)
- 睡眠環境を整える(枕・マットレス)
これらの積み重ねで、
「朝の軽やかさ」「日中の集中力」「家族との笑顔」が確実に変わります。
眠りを整えることは、ママや子どもへのいちばん身近なプレゼント。
ぜひ今夜からひとつ試してみてください。
きっと明日の朝、子どもの「おはよう!」がもっと嬉しく感じられるはずです。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
少しでも読者のみなさんのためになる記事作りにこれからも努めて参りますので、
評価していただけるととても励みになります☆
「こどもたちの未来をもっと明るくしたい」だから行動する。
それでは今日も元気にいってらっしゃーい(`・ω・´)ゞ
あるいはおやすみなさーい(。-ω-)zzz. . .

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd77e22.36bba099.4bd77e23.bc7ef352/?me_id=1353147&item_id=10000011&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmujina%2Fcabinet%2Fitem%2Fmujina0008%2Fmujina0008_top.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd78230.fc94534a.4bd78231.ea98855b/?me_id=1416718&item_id=10000017&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frisopale%2Fcabinet%2Fprd-img%2Ffll-liio%2Ffll-liio_r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd786c0.d973d7ea.4bd786c1.8e04588b/?me_id=1253212&item_id=10019309&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmantubiz%2Fcabinet%2Fitems-sync%2F2303-1%2F80001715-logo-r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd787db.e99bfb07.4bd787dc.d88cea31/?me_id=1386109&item_id=10000138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftatsuhikokosume%2Fcabinet%2Fk1096%2Fimgrc0094156878.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd7885f.ab37acc8.4bd78860.6ad66523/?me_id=1343640&item_id=10001719&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fglobalroad%2Fcabinet%2Fearplugs%2Fko-denshi%2Fimgrc0097017219.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd78a9b.c717266e.4bd78a9c.e72b41a9/?me_id=1311571&item_id=10009412&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjibunmakura%2Fcabinet%2F11%2F01%2F8588-set-sn.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

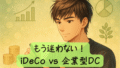
コメント