※この記事にはアフィリエイト広告が含まれております。
💡この記事はこんな方におすすめです
- 子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、どう受け止めればいいか悩んでいるパパ
- 共働きで忙しく、子どもとの時間が限られる中でも関わり方を工夫したいパパ
- 不登校や心の不調を「怠け」ではなく「SOS」として理解したい大人
- 家庭での居場所づくりや、親子でできる小さな体験を探している人
🐾 9月1日の意味を、パパ自身の問いに
9月1日――子どもの自殺が最も多い日とされています。
ニュースで耳にすると胸が締めつけられますが、
正直「自分の家庭には関係ない」と思っていませんか?
でも、もし自分の子どもが「学校に行きたくない」と言ったらどうしますか?
わたし自身、共働きで日々バタバタしながら子育てをしていますが、
子どもの小さなSOSを見逃してしまうことが一番怖いと感じています。
わたしは実際に、不登校のこどもと接する機会があります。
みんな元気で明るくてとてもいい子達です。
でも両親や学校の先生など近しい存在に対しては、
なかなか本音を伝えられていないように感じられます。
正直わたしのこども(息子こたぷん)が同じような「不登校」になったとしても、
今こどもたちと接しているようなやり方ができるとは思えません。
だからこそ、こどものSOSに敏感になることが大切なんです。
この記事では
「もし子どもが学校に行けなくなったら、パパとしてどう接するか?」
をテーマに、
社会の現実とわたし自身の経験を交えながら考えていきます。
🐾 なぜ9月1日に追い込まれるのか?背景を知る
夏休みが終わり、新学期が始まる9月1日。
多くの子どもにとっては「友達と会える日」ですが、
一部の子どもにとっては「また地獄が始まる日」です。
内閣府や文科省のデータによれば、
子どもの自殺理由の第一位は「学校問題」。
その内訳は、学業不振、いじめ、人間関係のストレス。
大人でも潰れそうな重荷を、まだ未熟な心で背負っているのです。
学校に戻ることが「苦しみの再開」となってしまう現実を、パパとして無視できません。
わたしたちが「普通に学校へ行くのが当たり前」と思っていること自体が、
子どもを追い込んでしまうこともあるのです。
今ではオンラインで全国、世界の人々とつながることが可能です。
もちろん学校に行くことを否定するわけではないですが、
選択肢を与えてあげることも、大人の努めなのです。
🐾 不登校はSOS。怠けではない理由
「学校に行きたくない」と言える子は、まだ救いを求めている証拠です。
ですが、本当に追い詰められるた時というのは、声に出すことすらできず、
体調不良や無表情といった “無言のSOS” しか出せなくなります。
パパとして一番大切なのは「怠け」と決めつけないこと。
次のパートで詳しく話しますが、
わたし自身も休職したときに、「自分は弱い」と思い込んでいました。
でも本当は心が限界に達していただけだったのです。
子どもの「学校に行きたくない」という言葉は、
「もうこれ以上がんばれない」という叫びです。
その声をどう受け止めるかで、未来は大きく変わります。
まずはしっかり、こどもの声に耳を傾けること。
声を出してくれなくても、粘り強く接し続けることがいちばんの近道なのです。
🐾 パパ自身の “心の不調” 体験談
わたしは転職後、とある部署に配属されたとき、
人間関係のギスギスした職場環境に心を壊しました。
先輩の心ない言葉、成果を認められない毎日、そして「居場所がない」と感じる孤独。
毎朝、出勤するだけで胃が痛くなり、夜は眠れない。
気づけば4か月の休職――まさに “大人の不登校” でした。
そのとき父から言われた言葉が忘れられません。
「うつ病は心が風邪を引いたようなもの。
風邪なら休めば治るんだから、今はゆっくり休めばいい」
弱さを責めず、ただ寄り添ってくれる存在がいること。
それが、立ち直る力になりました。
大人でも壊れるのだから、
子どもに「がんばれ」だけを押しつけるのは酷すぎます。
パパ自身の経験を振り返ると、
子どもの不登校が「心を守るための行動」だと理解できるのです。
🐾 どう寄り添うか?具体アクション集
パパができることは小さいけれど、その積み重ねが子どもを救います。
例えば――
- 言葉を否定しない:「怠けるな」ではなく「つらいよね」と返す。
- 小さな変化に気づく:食欲や睡眠の乱れ、笑顔の減少に敏感になる。
- 解決を急がない:「こうすればいい」と答えを出すより「話を聴く」に徹する。
わたしたちはつい “父親として解決したい” と思いがちですが、
子どもが求めているのは答えではなく「味方でいてくれる安心感」なのです。
わたしも子育て支援を通して、よくパパさんたちと交流していますが、
「味方でいること」「大好きでいること」を常に伝え続けている方々がほとんどです。
子育てサロンの代表であるわたしの方が、むしろ刺激をもらっています。
🐾 家庭でつくる安心の居場所
不登校になったとき、
家庭は子どもにとって最後の安全基地になります。
- 一緒に朝ごはんを作る
- 学校の話を無理に聞かず、雑談でつながる
- 休日は近所を散歩するだけでもOK
「学校に行けない」=「家で何もしてはいけない」ではありません。
むしろ、家で安心して過ごせる時間を持つことが、回復の第一歩になります。
家の中に「安心できるリズム」を作るのは、
忙しいママよりもパパが得意な場合もあります。
子どもにとって “パパと過ごす時間=ホッとできる時間” になれば、
それだけで命を守る力になります。
🐾 小学校高学年・中高生に向けた実践例
子どもが成長してくると、
ただ一緒に過ごすだけでは物足りないこともあります。
小学校高学年や中高生向けには、
少し「自分の存在を認められる体験」を意識することが大切です。
- 役割を任せる:家の中で小さなプロジェクトを一緒にやる(料理、DIY、旅行計画など)
- 好きなことに没頭できる時間を応援する:音楽、ゲーム、イラストなどを「それいいね」と認めてあげる
- 外の世界に触れるきっかけを作る:近所の図書館やカフェで勉強する、小さな旅に出るなど
「学校に行けない」ことに焦点を当てるのではなく、
「何ならできるか」に目を向けると、子どもは少しずつ前を向けるようになります。
🐾 相談先を知っておく
当然、ママやパパ一人ですべて抱え込む必要はありません。
専門の相談窓口があります。
- 24時間子供SOSダイヤル:0120-0-78310
- チャイルドライン:0120-99-7777
- いのちの電話:0120-783-556
- 児童相談所虐待対応ダイヤル:189
「助けて」と言える場があることを、パパも知っておくことが大切です。
いざという時に子どもと一緒に頼れる場所を知っているだけで、安心感につながります。
🐾 地域とのつながり・親子で楽しむ工夫
心のケアは、専門家につなげるだけでなく、
日常の「楽しい時間」を一緒に過ごすことでも育まれます。
- 地域イベントに参加する:夏祭り、地域清掃、体験型ワークショップ
- 一緒にごはんを楽しむ:食べログやぐるなびなどを使って近場のお店を探し、親子で“新しいおいしい体験”をする
- 自然に触れる:公園や河川敷を散歩するだけでも気分は変わります
子どもにとって「外の世界=怖い場所」から
「外の世界=楽しい場所」へ変えていくことが、再び挑戦する勇気につながります。
🐾 さいごに:パパが “味方” であるということ
9月1日は「子どもの命が最も危険にさらされる日」。
けれど、パパが気づき、寄り添い、つなぐことで「命が守られる日」に変えられます。
わたしたちパパにできるのは、完璧な答えを出すことではありません。
「大丈夫だよ、味方だよ」と伝え続けること。
その一言が、子どもの未来を支える力になるのです。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
少しでも読者のみなさんのためになる記事作りにこれからも努めて参りますので、
評価していただけるととても励みになります☆
「こどもたちの未来をもっと明るくしたい」だから行動する。
それでは今日も元気にいってらっしゃーい(`・ω・´)ゞ
あるいは、おやすみなさーい(。-ω-)zzz…
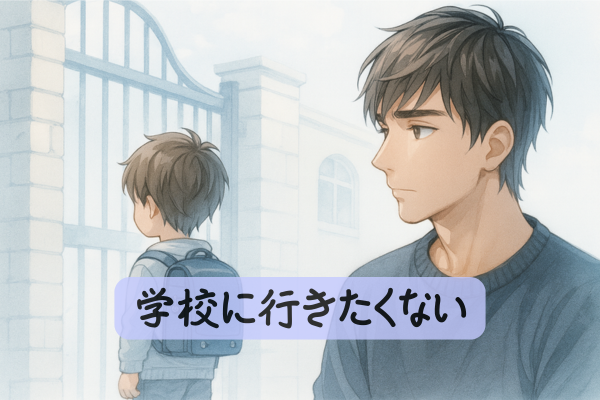
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd6f86a.82297b12.4bd6f86b.5c78085a/?me_id=1414045&item_id=10006071&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffuturshop%2Fcabinet%2Fladies1%2Fbotomusu%2Fdertyhw4ert.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd6f66e.313fa9d6.4bd6f66f.f4e2207b/?me_id=1385906&item_id=10003915&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff261009-kyoto%2Fcabinet%2Fr_travel_cp%2F2412rtc003.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd6f4a2.cf69c220.4bd6f4a3.90eda530/?me_id=1400011&item_id=10000063&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff122271-urayasu%2Fcabinet%2F10491031%2Fimgrc0109056190.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント