※この記事にはアフィリエイト広告を含みます。
🎯この記事はこんな方におすすめです
- 共働きで、保育園からの急な呼び出しにいつもヒヤヒヤしている
- 頼れる親族が近くにいない核家族家庭
- 「ベビーシッター」や「病児保育」が気になるけど、正直ちょっと不安
- 子育ても仕事も大事にしたいけど、どちらも中途半端になっている気がする
- 「パパとして何ができるのか」模索している
そんなあなたに、「頼ることは弱さじゃない」というメッセージを込めて、
わたし自身の体験と、外部サポートを活用するための実践的なステップをまとめました。
🐾 共働き家庭を襲う「保育園からの急な呼び出し」
「お子さん、熱が出ました。すぐにお迎えをお願いします。」
──たったこの一言で、一日の予定が一気に崩れ去る。
わたしも何度も経験しました。
会議の途中、商談の直前、出張先で。
どんなに綿密にスケジュールを組んでいても、
子どもの体調はコントロールできません。
そして、「どちらが迎えに行く?」という現実的な判断を迫られる。
その裏には、こんな感情が隠れています。
- 「仕事を抜けるのは迷惑かも…」
- 「パートナーに負担をかけたくない」
- 「子どもがつらいのに、すぐ行けない自分が情けない」
頭では「仕方ない」とわかっていても、
心はいつも少しだけ罪悪感を抱えてしまう。
共働きの親にとって、“呼び出しの電話”は避けられない現実。
だからこそ、そこに備える術を持つかどうかが、
心の余裕を左右する――そんなことを痛感しました。
🐾 気づき:「助けを持っておく」ことが最大の備え
あの日、夕方にやっと駆けつけた保育園で、
ぐったりした息子を抱きしめながら思いました。
「これ、わたしだけの問題じゃないよな。」
周りを見れば、みんなそれぞれの事情を抱えている。
実家が遠い、親もまだ働いている、頼れる知り合いがいない。
“孤育て”という言葉が現実味を帯びてきます。
でもそのとき、ふと気づいたんです。
育児を「誰かに手伝ってもらうこと」は、恥でも甘えでもない。
家族を守るための“戦略”なんだ。
頼る力を持っていることこそ、家族を支える「備え」。
この気づきが、わたしの子育て観を大きく変えました。
🐾 外部サポートってどんなもの?(具体例つき)
外部サポートと聞くと、
「ハードルが高そう」「お金がかかりそう」と思うかもしれません。
でも実際には、いろんな形があり、家庭に合った使い方ができます。
🩺病児・病後児保育
子どもが病気のときに、保育士や看護師資格を持つスタッフが見守ってくれるサービス。
施設型・訪問型のどちらもあり、
「熱が下がらないけど仕事が休めない」というときの心強い味方。
🧒ベビーシッター・訪問保育
自宅に来てもらい、保育園の送迎や一時的な預かりをお願いできる形。
「夜だけ」「30分だけ」などピンポイントで依頼できる柔軟さが魅力。
🏘ファミリーサポートセンター
自治体が運営する地域の助け合いネットワーク。
“おすそわけのような支援”が特徴で、費用も比較的リーズナブル。
こうしたサービスを知るだけでも、
「もしもの時の道」が一本見えてくるんです。
🐾 頼る準備を整える3ステップ(実践マニュアル)
ステップ①:情報を集める
まずは 「知る」ことから始める 。
自治体や保育園の掲示板、地域の子育て支援センターに情報が眠っています。
「病児保育」「ファミサポ」「一時預かり」で検索してみてください。
👉 事前登録や面談が必要な制度が多いので、元気なうちに準備するのが鉄則。
わたしも、これを後回しにして後悔したことがあります…。
ステップ②:サービスを比較してみる
いざという時に頼れるように、候補をいくつかピックアップ。
そのうえで、以下のポイントをチェックしておくと安心です。
- 利用できる時間帯(夜間・休日・当日対応)
- 料金体系(時間単価・交通費・登録料)
- スタッフの資格・経験・保険加入
- 利用者の口コミ(丁寧さ・連絡の早さ・安心感)
💬「値段より“信頼”を買う」という感覚で選ぶのがポイント。
わが家は、“対応の丁寧さ”を最優先にしました。
ステップ③:お試し利用で“距離感”をつかむ
どんなに評判が良くても、実際に頼んでみないと分からないことがあります。
だからこそ、いざという時の前に一度トライしておきましょう。
わたしは「夕方30分だけ送迎+見守り」をお願いしました。
その結果、息子の笑顔を見て「これなら任せられる」と確信。
小さな一歩が、大きな安心につながりました。
🐾 使ってみて分かった、3つの“変化”
① 仕事への集中力が戻った
外部サポートを登録してから、
仕事中の「もし保育園から電話が来たら…」という漠然とした不安が消えました。
それまでは良くも悪くも、
会議の最中でも頭のどこかで子どものことを考えてしまっていた。
「熱出してないかな」
「妻は今日は在宅だっけ?」
——そんな心配が常に脳の片隅にあって、
正直、仕事に“全力で集中できていない自分”がいました。
でも、「いざという時は、お願いできる人がいる」と思えるようになってからは、
心の中の“予備バッテリー”が増えた感覚。
仮に呼び出しが来ても、
「大丈夫、手はある」と冷静に判断できるようになりました。
結果として、仕事のパフォーマンスも上がったんです。
上司や同僚から「最近、落ち着いてるね」と言われるようになったのもこの頃。
「頼れる仕組みを持つことは、仕事の責任を手放すことではない。
家族も仕事も守るための、正しいリスクヘッジなんだ」
この気づきは、わたしにとって大きな転換点でした。
② 家庭の空気が穏やかになった
以前の我が家では、
急な呼び出しがあるたびに、夫婦の間にピリッとした空気が流れていました。
「今日はあなたが迎えに行ってよ」
「いや、そっちのほうが早く終わるでしょ?」
誰も悪くないのに、気づけば小さな不満が積もっていく。
“どちらが我慢するか”の駆け引きが、
知らないうちに夫婦の間の温度を下げていたんです。
でも、外部サポートを導入してから、
この「どっちが行く?」という議論が、自然となくなりました。
「今日、もし呼び出しがあったら、○○さんにお願いしようか」
──そんな風に “頼れる第三の選択肢” があることで、
夫婦の会話のトーンが柔らかくなった。
「お互いの予定を守りながら、ちゃんと子どもも守れる」
その安心が、家庭の空気を穏やかにしてくれた気がします。
夜、子どもを寝かしつけたあと、妻がポツリとこう言いました。
「最近、家がちょっと明るくなった気がするね。」
あの言葉を聞いた瞬間、
「頼る」って、家族全体を守ることなんだと心から思いました。
③ 子どもに“安心できる大人”が増えた
正直、最初は“他人に子どもを任せる”ことに抵抗がありました。
「泣かないかな」「怖がらないかな」と、こちらがドキドキしていたほど。
でも、実際にお願いしてみると、
子どもは10分も経たないうちに笑顔で遊び始めた。
帰宅したわたしに向かって、
「パパ、あのお姉さん、また来てくれる?」って聞いたときの顔。
それがもう、忘れられません。
わたしはその瞬間、
「子どもにとって“安心できる大人”は、親だけじゃなくていいんだ」と思いました。
それは“親の役目を奪われる”ことではなく、
“子どもの世界を広げる”こと。
社会の中で、いろんな大人に触れ、いろんな言葉を聞く。
それが小さな経験の積み重ねになっていく。
親が一人で頑張るよりも、
周囲の大人と一緒に“子どもを見守る”ことが、
どれほど豊かなことかに気づかされました。
今では息子も、
保育園の先生やサポートさん、近所のおばあちゃんまで、
みんなを信頼して笑顔で話すようになりました。
「子どもを真ん中に、大人たちがゆるくつながる」
そんな関係を築けることこそが、
今の時代の“子育て力”なのかもしれません。
💬よくある質問(FAQ)
Q1. 初めて預けるとき、泣かないか心配です。
A. 最初は当たり前。短時間から始めて慣らしていきましょう。
好きな絵本やぬいぐるみを渡しておくと安心材料になります。
Q2. 当日依頼はできる?
A. サービスによりますが、事前登録さえしておけば可能なところも多いです。
事前準備こそが最大のポイントです。
Q3. お金がかかるのでは?
A. “使う頻度をコントロールする”のがコツ。
我が家は「月に2〜3回・短時間」で無理なく続けています。
Q4. 安全面が心配。
A. スタッフの身元確認・保険加入をチェック。
口コミで「連絡が丁寧」「子どもが懐いた」などの声が多いサービスは安心材料です。
🐾 完璧じゃなくていい。準備している親でいよう
子育ては、家族だけでは抱えきれない瞬間が必ずあります。
それを“情けない”と感じていた昔の自分に、今ならこう伝えたい。
「頼ることは、家族を守る勇気だよ。」
共働き、核家族、遠方の実家──それでも、
「もしもの時にお願いできる相手」がいるだけで、毎日が軽くなります。
完璧じゃなくてもいい。
でも、“子どものために準備しているパパ”でいたい。
それが、わたしの今の目標です。
🌱おわりに
子育ては、時に孤独です。
でも、“頼る仕組み”を一つ持つだけで、世界がやわらかく見えてくる。
わたし自身、あの「熱が出ました」の電話をきっかけに、
パパとしての考え方が変わりました。
「こどもたちの未来をもっと明るくしたい」
だから、まずは親である自分たちが、余裕と選択肢を持つこと。
それが、家族の笑顔を守る最初の一歩だと思っています。
今日も、わたしと同じように奮闘しているあなたへ——
一緒にがんばっていきましょう。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
少しでも読者のみなさんのためになる記事作りにこれからも努めて参りますので、
評価していただけるととても励みになります☆
「こどもたちの未来をもっと明るくしたい」だから行動する。
それでは今日も元気にいってらっしゃーい(`・ω・´)ゞ
あるいはおやすみなさーい(。-ω-)zzz. . .

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1dbdba.e3384c85.4e1dbdbb.0a8aeb45/?me_id=1248281&item_id=10125319&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flock110%2Fcabinet%2F12144337%2F101001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47a583f8.f7dff604.47a583f9.053e3244/?me_id=1337032&item_id=10000192&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-tech-rshop%2Fcabinet%2Fpicturebook%2F9784799109472%2Fikijisyo-samune.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d0d03c5.c32c6fbe.4d0d03c6.d16013f6/?me_id=1385805&item_id=10000020&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftcconlineshop%2Fcabinet%2F08948437%2Fcompass1653472205.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ccee450.d899c33c.4ccee451.47fa220b/?me_id=1346082&item_id=10000468&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstore-ecovacs-japan%2Fcabinet%2Fcampaign%2F251104%2Fddx57-12ee.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1dca6f.9e5bc24c.4e1dca70.ba10a013/?me_id=1287664&item_id=10000034&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faircon-clean%2Fcabinet%2F10394214%2Fac101.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1dc8fa.d1a2e252.4e1dc8fb.b3d85a75/?me_id=1224832&item_id=10003282&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbaby-smile%2Fcabinet%2Fa01%2Fr0101bta2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1f67b2.03771c41.4e1f67b3.9f34e5fa/?me_id=1194161&item_id=10000640&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fu-can%2Fcabinet%2Fitem%2Fthmb_1546_r2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
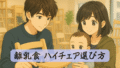
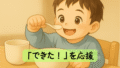
コメント